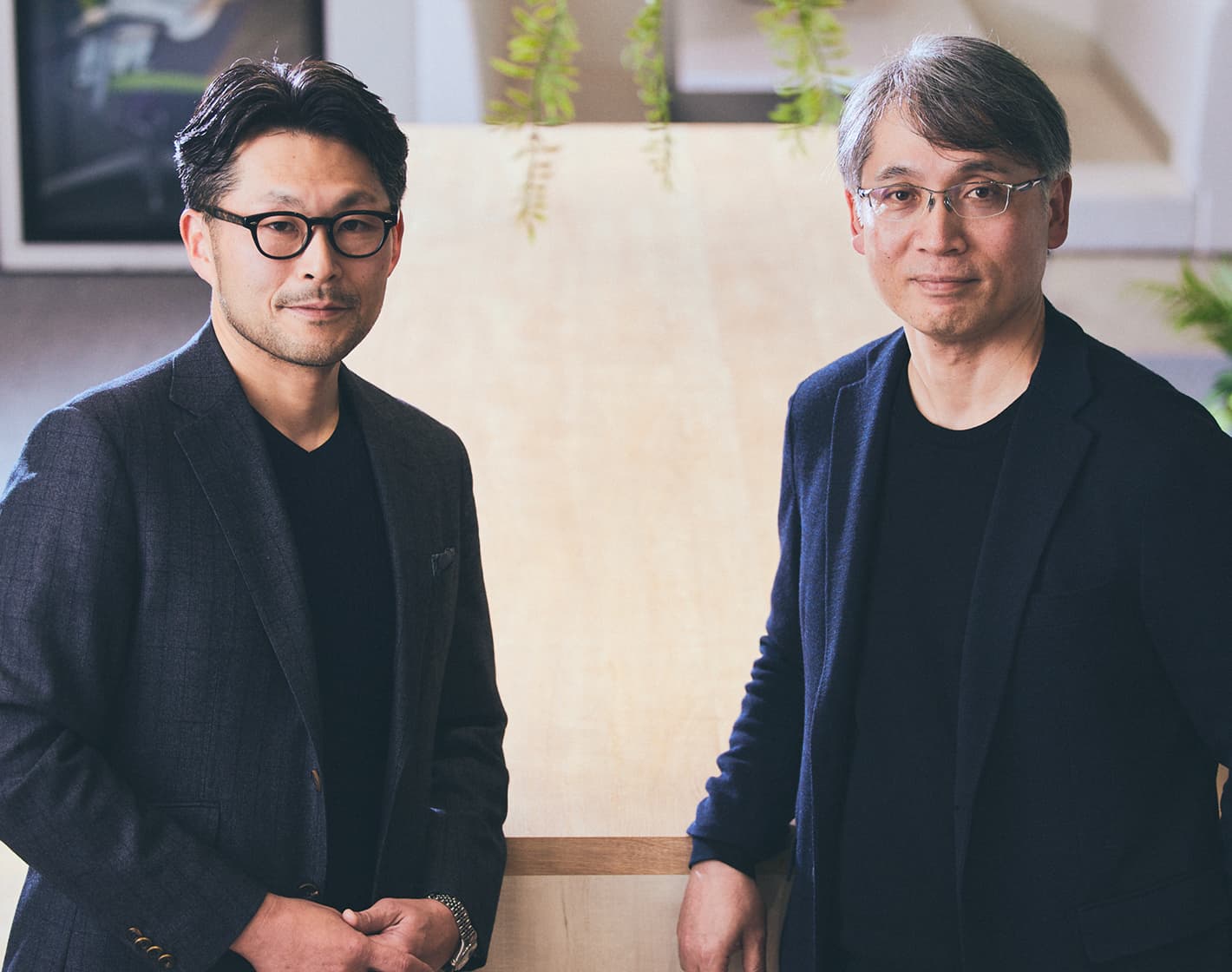本来、コンサルタントの
いない世界が美しいのか。
――本日は、よろしくお願いいたします。早速ですが、石原さんは日置さんからいただいた言葉で、ぜひお話ししたいことがあると伺いました。

はい、日置さんが以前「コンサルタントは”必要悪”だ」とおっしゃっていたことをよく覚えています。私自身も同じ考えを持っており、「コンサルタントが不要な世界こそが、本当は美しいんじゃないか」とすら思います。日置さんはコンサルタントの役割や必要性について、どのようにお考えですか?

美しいかは別として「コンサルティングが常に存在し続けるべきもの」という前提で物事を考えるのは、違和感がありますね。そもそも、コンサルティングは『外野産業』です。つまり、企業が常に自立的に経営することができていれば、本来は不要なはずです。しかし、企業は多様な変化に直面しています。特に、将来を予見することがますます難しくなる時代、すべての事象に自社だけで対応することは困難であり、時には外部に頼らざるを得ない。変化が続く限り、コンサルタントは、存在し続けると思います。もちろん、経営者にとって「必要”善”」と捉えていただけるのが理想ですが、個人的には「必要”悪”」的なファンクションと考えています。
だからこそ、コンサルティング業界が日本における「成長産業」としてもてはやさられる現状には、違和感を覚えます。コンサルティングはあくまで企業の成長を支援する補完的な機能であり、極論ですが、自らは何も生み出せません。そう考えると、国や事業会社が成長のあり方を模索し続けている中、業界の成長を単純に喜んでよいのかは疑問が残ります。

なるほど。必要性はあるものの、コンサルティングはあくまで「外野産業」であり、現在のコンサルティング市場の過熱感には違和感があるということですね。それで言えば、本来企業が主体的に考えるべき領域まで、外野であるコンサルタントが担ってしまっているのではないか?と感じます。業界自体が、その構造をつくってしまったのかもしれません。例えば、中期経営計画(中計)の策定すらコンサルタントに委託してしまうケースがありますが、これについては、どのようにお考えですか?

中計の策定を外部に任せるということは、自分の未来を人に預けるという話じゃないですか。個人的には「それって面白くないでしょ?」とは思いますね。一方で、そうした状況が生じている背景をしっかりと理解しなければ、企業とコンサルタントの健全な関係は築けないと感じます。
――未来の戦略を策定することが経営だとすると、コンサルタントに中計の策定を任せてしまう理由には、経営者が経営をしていない状況があるのでしょうか?

事業戦略はあっても企業戦略がないと言われがちな日本企業とは言え、経営者が経営してないということではないと思います。ただ、純粋に会社を成長させることに集中できる時間は限られています。特に昨今では、国や資本市場含めて社会からの要請事項も増え続けており、内部リソースだけでは対応が難しくなっています。結果、経営層からコーポレートスタッフまで本業以外の業務に多くの時間を奪われてしまい、外部のコンサルタントの力を活用せざるを得ない状況になるのではないのでしょうか。
こうした状況の中であっても、長期ビジョンや新規事業などの重要な経営アジェンダにどれだけの社内のリソースや時間を確保しようとするのか。この点を整理することで、コンサルタントに求める役割もより明確になり、効果的な支援を受けられるようになると思いますね。

どんな企業や人が、コンサルタントをうまく活用できていると思いますか?

圧倒的にオーナーシップを強く持つ経営者がいる企業ですね。創業経営者はもちろんのこと、サラリーマン経営者であっても。そのような経営者は、社内外問わず、どのようにリソースを活用すべきかを主体的に考えており、その姿勢がコンサルタントの活用において重要だと考えます。もちろんこれは、経営者に限った話ではなく、部門の責任者層から担当者であっても大事なことで、コンサルに求めることがクリアになります。実際、グローウィン・パートナーズ(以下、GWP)の顧客層である中堅企業は、オーナーシップを持ち続けやすい環境にある経営者が多いと思いますね。こうした経営者や企業とのお仕事は、非常にやりがいがあり、すごく面白いんじゃないでしょうか。

確かに。中堅企業をご支援させていただくと、明確にオーナーシップを持たれていると感じます。一方で、コンサルタント自身にオーナーシップがなければ、「要らないよ」と判断されてしまうこともあるでしょう。オーナーシップは、ある種の使命感とも言えるかもしれませんが、それはどのように生まれてくるものなのでしょうか。

どうやって生まれるんでしょうね。ただ、一概には言えませんが、必ずしも特別な素養が必要ではないと考えます。そもそも、人である以上、完璧ではなく、使命感を持つこと自体が容易ではありません。例えば、戦後の経営者たちが、「日本を立て直したい」という強い使命感を持っていたのは、敗戦の荒廃という当時の環境が影響したところもあるでしょう。一方で、現代は恵まれた環境であり、生きていくために不可欠なという温度感のものは自然とは生まれにくくなっているのかもしれません。他方で、社会が発展したらしたなりにまた別の類の課題が生じてきます。自らの原体験を基に社会課題解決を掲げるスタートアップやNPOの経営者が増えているのは新たな流れであり、これはこれで素晴らしいことです。
ただ、1つの使命感に無理に固執し続けるのは違う気がします。アメリカでは、新しい企業が新しい産業を牽引する傾向がありますが、日本の場合は、既存企業が新しい産業でなんとか生き残ろうとする。その時点で既存の慣性に引っ張られるなどスピード感が遅いわけです。もしかすると、企業も無理に存続し続けるのではなく、使命を果たしたら潔く撤退するという選択肢も、美しいのかもしれません。

企業としての動態を見つめ、
変化に合わせた体制を築く。
――お二人ともありがとうございます。先ほど、経営者が経営する時間をどう確保し、どう使うかという話がありましたが、結局、リソース不足が経営における課題なのでしょうか。

いや、リソースが十分に確保できることは永遠にないと思います。また、「人材が課題」という企業も多いですが、人材が課題でなくなる時もないと思います。この前提の上で、限りあるリソースをどう活用し、どのように補うのかを考えることこそが経営の在り方ではないでしょうか。

これは私自身の経験も踏まえて感じますが、中堅企業のCXO(最高責任者)は何かを兼任しているケースが多く、それにより業務負担が増大し、重要な経営アジェンダに十分な時間を割けていないことが少なくありません。そのため、GWPでは、CXOが本来の役割に集中できるよう、「コーポレート機能」に従事している方々を支援する体制を整えています。

コーポレート機能に従事している人たちの中から、いずれ経営を担う人財も生まれていく。その点では、今の経営陣の支援をしながら、将来の経営人財と企業の成長基盤創りを長期にわたって支援し続けているGWPさんの大きな差別化ポイントでもありますよね。長い目で見て、伴走者、パートナーとしての位置付けができている。私は「経営をしてないコンサルタントが経営を語るな」と思いますが、長期的にお付き合いを重ねることで、少しは解消されると思います。数ヶ月のプロジェクト単位のみでの関りだと、企業の全体像を理解するのは難しいですが、1年、2年、3年とお付き合いを続けると、経営会議や予算策定、人事異動など、社内の主要なイベントサイクルから、組織や人の動き方までを深く理解できるようになります。プロダクトの専門性をつけることも重要ですが、同時に企業の動き方をしっかり学ぶ姿勢がなければ、コンサルタントとして続かないと思います。

ありがとうございます。特にCFOを中心に、その方の専門領域以外をどうサポートし、どのように体制を構築するかが、我々の価値発揮できる部分だと思っています。

中堅企業におけるCFOは、いわば番頭さんのような存在であり、金も人も見ますが、すべてを見切るのは難しいところです。ですから、どんな体制でサポートしていけるか、そして、企業の成長に応じて構造を変えていけるかが重要です。

そうですね。とはいえ、トップの意思決定が不可欠です。CFOはじめとするCXOや、周囲のメンバーが変わるためにも、経営のトップが事業をどう変えるか、その意思が示されない限り、なかなか変化は起きないですよね。

「やり方だけを変える」だけで、企業が変革するケースはあまり見たことがないですね。事業としての「やる事」や、その総体としての企業の「あり方」を変えることで、やり方も変わる。昔話しになりますが、例えば、IBMは1993年の危機を契機に、グローバル企業としてのそれまでのあり方を見直しました。事業構造についても、ハードからソフトへの転換を図っていきました。一連の変革の過程で、コーポレート機能やコーポレートスタッフの在り方も変わりました。あり方ややる事を変えていく過程でこそ、組織やプロセス、そして人の動きも変わっていくのです。ですから、コーポレートに従事するスタッフや機能を変革するためには、自らを含めたCxOのあり方を問い直すという経営トップの姿勢が不可欠なのです。

トップが動かなければ組織は動きませんよね。GWPでもまさにビジネスと組織の変革に取り組んでいます。変化という文脈で考えたとき、変化に踏み出せない企業や経営者にはどんな悩みがあるのでしょうか。

先ほどの「使命」の話にもつながりますが、最も大きな悩みは「そもそもどの程度変化する必要があるのか分からない」という点にあると思います。企業は環境に適応しながら成長する必要があると理解していても、具体的にどのような変革を進めるべきかを見極めるのは容易ではありません。特に、社内で認識している変化のスピードと、外部環境の変化のスピードにギャップがあると、「そんなに急いで変える必要があるのだろうか?」という疑問を持つ気がします。

たしかに、「変化しなければ危ない」と言われても、もし1000億円を稼げるビジネスが目の前にあったら、「別に潰れないしな」と思ってしまうリアルもあります。

そうした神学論争に対して、ファクトを提供するというのも、コンサルタントの重要な役割かもしれないですね。

分からないことを、
分かっている人がいい。
――変化スピードの話がありましたが、自分たちの時代は良くても、10年後、20年後を見据えた時に、どのように対応するべきかという未来の話もあると思います。

そうですね。私には、高校生と中学生の娘がいるのですが、数年後に社会に出るときに、彼女たちは変化し続けられるだろうか?生き抜いていけるだろうか?と漠然と考えます。個人の変化だけでなく、企業もそれに合わせて一緒に変化できる、そんな世界を作りたいと思うときに、何ができるのかを常に模索しています。

将来の世界を作るのは若者たちであり、彼ら自身が未来を切り拓いていくと私は考えています。しかし、その過程において障害や制約になりそうなことがあれば、それを取り除くのは先行する私たちの世代の責務だと考えています。50年後の世界にいない私たちが「こうすべきだ」と無責任に決めつけることはできませんが、少なくとも未来の可能性を狭める要因は減らしていくべきだと思います。

本当にその通りですね。「こうしなさい」と指示するのではなく、障害を取り除くことが私たちの役割だと思います。

国が縮んでいくという現実を直視しつつも悲観的になり過ぎずに、日本にとって心地よいあり方をどう見つけていくか、それをみんなで議論できる環境をどうつくるか、そのために制約をなくしていくことはできると思います。そうやって、考え続けることが大切だと感じています。唯一絶対の解が存在する訳ではありませんので。

変化のスピードが加速したときのために制約を取り除くことは、経営陣にとって非常に重要な役割の一つかもしれません。

企業と長期的に付き合う意義は、その点でも重要だと考えています。企業のことを深く理解しているからこそ、変化のスピードに対して「いまは静観しても問題ない」「ここは今すぐ対応すべきだ」といったアドバイスができる。文字通り「パートナー」であり続けることが重要だと思います。大企業は変数が多く判断が難しい部分もありますが、中堅企業であれば、そのような伴走支援が可能なのではないでしょうか。
――ありがとうございます。変化の中での経営において、コンサルタントが果たすべき役割についてお話しいただきましたが、改めてコンサルタントとして何を大切にしてほしいと思いますか?

私が若かりし頃、何度もお客様に厳しい指摘を受けるとともに、ご指導も受け、育てて頂いた経験があります。そういう関係値を築けるコンサルタントであってほしいと思います。「出来ないことでも一生懸命考え、自分なりの答えを出す」という姿勢が重要だということです。お客様に「あなたの会社をどう思っているか」を率直に伝えることが信頼を築くきっかけになります。そのためには、仮設ではなく、実体験をもとに話をし、お客様から学びを得、お客様にも学びを提供しあえるような関係を築くことが大切です。オーナーシップの強い人に対しては、ロジカルに話すだけでは「だから?」と一蹴される世界のため、論理を超えて、相手の視点に立ち、行動することをいとわず、本質的な対話ができることがより重要ではないでしょうか。

以前、若い方から「ロジカルシンキング」について尋ねられた際に、「ロジカルシンキングは、普通に考えることだ」と答えました。結局、テクニカルに難しいことではなく、自分の中の「普通」のレベルを高めるための鍛錬が大事だと思います。

その通りです。企業として学べる環境を提供しますが、実際にそれをいかせるかは自分次第だと思います。

現在は情報をキュレーションしやすい環境ですから、知らないことが恥ずかしいという風潮もありますね。最近、某コンサルティングファームのシニアパートナーと「どんな若手が理想か?」という会話をした際、私は「分からないことを分かっている人がいい」と話しました。そういう人は、的確な質問ができるからです。逆に、分からないことをそのままにして、そこにキュレーションした情報を並べて取り繕う人には「何が分かってないのかが、分からないのだろうな」と感じてしまいます。そういう人ほど「仮説」という言葉を間違って使いがちです。

「分からないことを分かっていること」はすごく大事ですよね。カッコつけてもすぐに見抜かれてしまいます。まさに今日も、日置さんとお話しするにあたって、弊社メンバーには「かっこつけようとするとすぐに見透かされるから、自分が考えていることを素直に伝えるように」と伝えました(笑)。ただし、それには十分な準備が必要ですね。
本日の対話を通じて、変化の時代における企業経営と、コンサルタントとしての在り方について改めて考えさせられました。未来を見据えたとき、私たちはどのような価値を提供し、どのように貢献できるのか。その問いを持ち続けることが、プロフェッショナルとしての成長につながるのかもしれません。
私たち自身も、クライアントとともに学び、自分たちの経営を通じて実践を積み重ねながら、より良い未来をつくるために行動していくことが求められています。その意識を持ち続けながら、これからも挑戦を続けていきたいと思います。

こちらこそ、今日はありがとうございました。